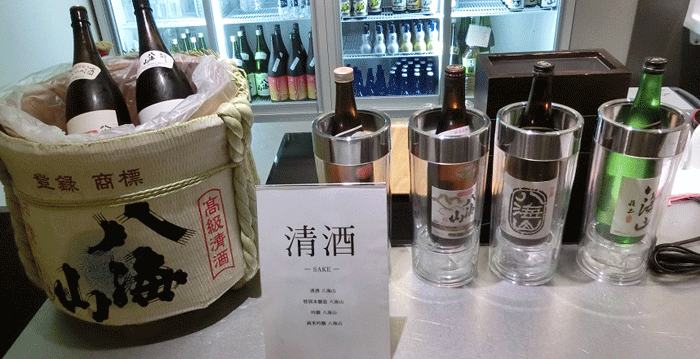第217回《1998年1月より》 日本酒と料理を楽しむ会
2015年9月25日開催
「八海山」日本酒セミナーと、「発酵料理」
今月は、特別企画として
日本酒の地酒蔵が、今なにを考え、今後どこへ向かおうとしているのか、
トップランナーである八海山の、「千年こうじや」へお邪魔して、
日本の将来を占う、超真面目な日本酒講座を開催しました!
八海山は以前から東京営業所を設け、そこにキッチン併設のセミナールームを持っています。
日本酒をもっと知ってもらい飲んでもらおうと、積極的に自主セミナーを公開するほか、
今回のように、希望者には貸切でセミナーをカスタムに開催してくれます。
セミナーテーマは、
改めての、日本酒の基礎を学ぼうと言うもの。
講師の余田さん(八海山の東京営業所)から、少し関西風の言葉遣いのよく通る声で
日本酒の定義から造りの各工程を、八海山のこだわり(独自性)を交えながら講義していただきました。
特に余田さんのこだわり“どうしてアル添が悪者扱いされるのか”という、今の日本酒イメージを払拭すべく
アル添酒の美味しさ、奥深さを熱弁。聴講生一同、純米酒ありきではないとの想いを新たにしていた様子でした。
添加用の醸造アルコールの99%が、ブラジル産サトウキビ蒸留酒で、大手商社から買っているというのは、初見でした。
テーマは、時には「発酵料理教室』などもあり、味噌づくりを体験できるなど
日本酒〜発酵技術〜発酵食品〜発酵料理と日本酒の相性の良さ〜日本食文化の基礎を学べるようになっています。
もちろん、この日も座学のあと、発酵料理のスペシャリスト・薮田さゆり先生の料理をいただきながら、
八海山を飲み尽くしました。
敢えて言えば、
我々の世代が3000以上もあった国酒の蔵元を1000にまで減らした、張本人です。
その負のトレンドがようやく止まり、次のステージが始まろうとしています。
しかしそれがどこへ向かうのか、どんな産業となり、飲み手にどれほどの価値を提供しうるのか?
それは、日本文化の新たな世紀にふさわしい形なのか?
一つのチャレンジが、八海山さんの2時間のセミナーに現れていると思います。
とてもいい企画になったかと思います!
<今月テーマ>
セミナー「日本酒基礎講座」 講師:余田岳志氏
【セミナー後に飲んだお酒】(写真上、菰樽の右から)
①「清酒 八海山」
②「特別本醸造 八海山」
③「吟醸 八海山」
④「純米吟醸 八海山」
われら日本酒愛好家のために特別調達していただいた(写真下左)
⑤しぼりたて原酒「越後で候」2009BY
⑥しぼりたて原酒「越後で候」2013BY
梅酒3種(写真下右)
⑦「清酒原酒 梅酒」「焼酎 梅酒」「焼酎にごり 梅酒」
写真にはないですが、八海山の造る
⑧地ビール「八海山 泉ビール」


「越後で候」は、やはり美味しいですね。
今月の会場は 八海山 「千年こうじや」セミナールーム 住所:中央区築地4−5−9 築地安田第二ビル8階
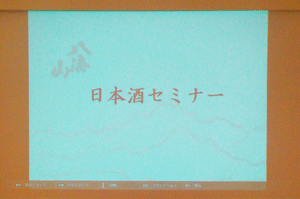
セミナールームは今年2015年9月改装(移転)され、備え付けのプロジェクター&スクリーンなど本格的。約1時間、みっちり勉強しました。

発酵調味料「塩麹」で味付けた「鶏ハム』。

「栃尾油揚げの 葱はさみ焼き」

セミナー会場はこんな感じ。写真奥が、キッチンとバーカウンター。中仕切りで音や臭いが漏れないようにもなります。着席定員は約30名。

あったか「麹入り おでん」。おでん種はもちろんですが、おつゆの美味いこと旨いこと。

発酵調味料/飲料の「あま酒甘酢の 菊花蕪」。

キッチン&バーカウンターへ移って、立食の乾杯。

茄子とピーマンの「揚げびたし」。
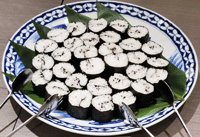
食事は「南魚沼産コシヒカリ」のおにぎりで締めました。
(2015年9月25日水曜日開催)
地酒蔵としては大手の八海山。その八海山が、蔵自身の成長と日本酒業界全体の発展を考えたとき、答えの1つとして出したのが首都圏での、セミナーという形。外国人向けセミナーなども大きな可能性を秘めているでしょうし、こうした常設施設を持つのが体力のある酒蔵のトレンドとなるかもしれません。
《日本酒と料理を楽しむ会 アーカイブ》
第210回以前の記録は右から辿ってください こちら
第211回150325開催の「秋田NEXT5」ときの字の料理は こちら
第212回150422開催の「結城酒造」と柏庵の料理は こちら
第213回150527開催の「車坂」「日本城」と京矢の料理は こちら
第214回150624開催「黒松仙醸」「こんな夜に」ときの字の料理はこちら
第215回150722開催の「玉川酒造」と柏庵の料理は こちら
第216回150824開催の「勢正宗」と「きの字」の料理は こちら